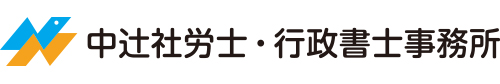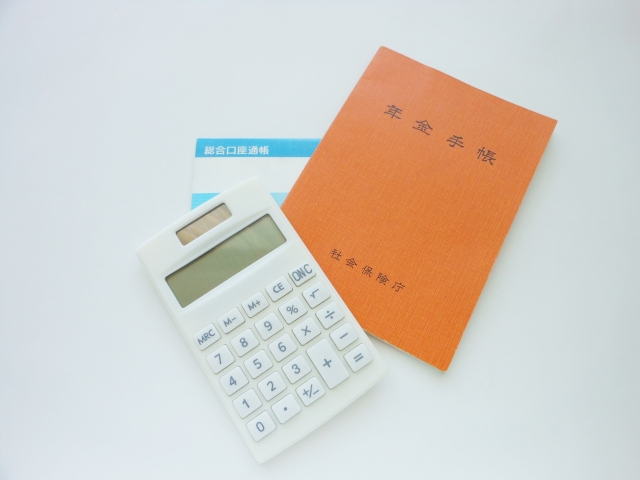
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害年金の申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。
当事務所では、障害年金の申請をスムーズに進めるためのサポートを提供しています。
受給要件
障害年金を受け取るには、①加入要件、②保険料納付要件、③障害状態要件の3つの要件を満たす必要があります。
①加入要件
<障害基礎年金>
・「初診日」に国民年金に加入していた方
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に「初診日」がある方
<障害厚生年金>
・厚生年金保険に加入している期間に「初診日」がある方
※初診日は、障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日となります。
②保険料納付要件
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間内に、保険料の納付済み期間が3分の2以上あること(保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間)
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
※初診日が令和8年3月末日までにあるときで、初診日に65歳未満であること。
③障害状態要件
障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める等級(障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級から3級)に該当していること。
※障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内に治った日(症状が固定し治療が終わった日)となります。
障害の程度
障害年金が支給される障害の状態に応じて、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。
| 障害の程度 | 障害の状態 | 活動の範囲 |
| 1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの状態。身のまわりのことはかろうじてできる程度。 | 入院や在宅介護が必要で、活動範囲がベットの周辺に限られる |
| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの状態。 | 入院や在宅で、活動範囲が病院内・家屋内に限られる |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。 | 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある |
障害基礎年金の年金額(2025年度)
| 障害等級 | 昭和31年4月1日以前生まれ | 昭和31年4月2日以後生まれ |
| 障害1級 | 1,036,625円 | 1,039,625円 |
| 障害2級 | 829,300円 | 831,700円 |
| 子の加算 | 生計維持をしている18歳未満の子がいる場合、2人目までは1人につき239,300円、3人目以降は1人につき79,800円 | |
障害厚生年金は、障害基礎年金の上乗せ年金として支給されます。年金額は、厚生年金保険の被保険者期間中の報酬月額をもとに計算され、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者の加算も行われます(1級および2級の場合のみ)。
申請の流れ
1
面談・ヒアリング
ご本人またはご家族様とお会いして、障害年金の申請に必要な情報をお伺いします。
2
年金記録の確認
保険料の納付要件を満たしているかを確認するため、年金事務所で年金記録の確認を行います。
3
受診状況等証明書の取得
「初診日」を証明するため、初診を受けた医療機関に連絡し、受診状況等証明書の作成を依頼します。
4
診断書の取得
現在の医療機関へ診断書の作成を依頼します。
適正な診断書が取得できるよう、日常生活で困っていること等をしっかり医師に伝えることが大切です。
5
病歴・就労状況等申立書の作成
最初に医者にかかった経緯から現在までの流れを記述します。
ご本人様と相談しながら申立書を仕上げていきます。
6
その他の必要書類の準備
年金請求書、戸籍謄本などの添付書類を揃えます。
7
申請窓口へ年金請求書を提出
年金請求の書類一式を年金事務所へ提出します。
報酬額
| 初回相談料 | 無料 ※ご依頼いただいた場合も、無料で対応いたします。 |
| 事務手数料 | 1万円+消費税 |
| 受給が決定した場合 ※①と②のどちらか高い方になります。 | ①振り込まれた年金の2ヶ月分相当額+消費税 |
| ②初回振込額の10%+消費税 | |
| 費用について | 診断書等の作成費用、戸籍謄本などはご依頼者様のご負担となります。 |
Q&A
-
障害年金の対象となる病気やけがにはどのようなものがありますか?
-
障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。
病気やけがの主なものは次のとおりです。
外部障害 眼、聴覚、音声又は言語機能、肢体(手足など)の障害など 精神障害 統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など 内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
-
初めて医師等の診療を受けた病院が廃院となっており、初診日を証明する書類を準備することができない場合は?
-
初診時の医療機関の証明が得られない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、ご本人の申し立てた日が初診日と認められる場合があります。
-
障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)から複数年経過していますが、障害年金は請求できますか?
-
障害認定日から1年以上経過している場合でも、障害認定日時点の障害の状態がわかる診断書と現在の障害状態(請求日前3ヵ月以内の症状)がわかる診断書を用意することにより、障害年金を請求することができます。ただし、5年以上前の年金については、時効により受け取ることができません。
お問い合わせ
ご相談、ご質問やお仕事のご依頼など、お気軽にお問い合わせください